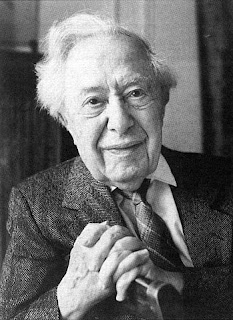その2.多様性
大学卒業時、
当時師事していブルガリア出身
(ルーマニアン・スクール)の
スヴェトラ・プロティッチ教授が、
多様でオープンマインドな
教育環境で勉強できる
教育環境で勉強できる
アメリカへ留学することを
勧めてくださいました。
アメリカには
ドイツ系、ロシア系、フランス系など
あらゆるバックグラウンドの
芸術家が
集まっているので、
集まっているので、
ある一定の地域に
根ざしている
(どちらかといえば)
(どちらかといえば)
画一的なメソッドを
習得するというよりも、
様々な伝統や流派を
見聞きすることで、
自分がめざす音楽に合った
スタイルやメソッドを
追求して学ぶことが
できるかもしれない、
とおっしゃいました。
*
19世紀から20世紀にかけて、
以下に挙げるような
ヨーロッパ、
なかでも
ロシア&ロシア周辺
(旧ソヴィエト連邦) や
東欧出身の
多くの音楽家が
アメリカで活躍しました。
作曲家:
ストラヴィンスキー(ウクライナ)
プロコフィエフ(ウクライナ)
バルトーク(ハンガリー)
ドヴォルジャーク(チェコ)
マーラー(オーストリア)
シェーンベルク(オーストリア)
ヒンデミット(ドイツ)
ブロッホ(スイス)
指揮:
ストコフスキー(イギリス)
バイオリニスト:
アイザック・スターン(ウクライナ)
ピアニスト:
チェリスト:
フォイアーマン(オーストリア)
ロストロポーヴィチ(アゼルバイジャン)
また、
ヨゼフ・レヴィーン(ウクライナ)
ナディア・ブーランジェー(フランス)
ナディア・ライゼンバーグ(リトアニア)
イザベル・ベンゲーローバ(ベラルーシュ)
といった、
伝説の名教師たちが
アメリカの
クラッシック教育の礎を
築きました。※1
さらに、
後に我が師となる
アルカディ・アロノフ(※2) は
1977年にサンクトペテルブルクから
米国へ移住、
同門(サヴシンスキー門徒)の
ヴィタリー・マルグリス や
ネイガウスの弟子の一人
ニーナ・スベトロノーヴァ
たちも
米国における
ピアノ教育の発展に
貢献しました(※3)。
*
私自身、
留学を決めた時点で、
具体的に
どの先生に師事したいかなど
音楽家としての方向性は
まだ定まっていませんでした。
ただ、
小さい頃から
ずっと聴いていた
旧ソ連のピアニスト
リヒテルへの憧れは強く、
また、
恩師プロティッチ教授の
同門にあたる
ディヌ・リパッティの
レコーディングを
19歳で初めて聴いた時は
凄い衝撃を受けました。
米国でレジーナ・ロヴィンの
孫弟子と勉強した
最初の師の影響もあり
物心ついたときから
旧ソ連や東欧のピアニズムには
深く影響を受けていました。
とはいえ、
アメリカを進めて下さった
先生ご自身も
アメリカに音楽関係の
コネクションやネットワーク、
コネクションやネットワーク、
留学に関する
具体的な情報を
お持ちだったわけではありません。
そのため
学校選びや
オーディションの段取りなど
自分でゼロから行うことに
なりましたが、
しがらみのない
未知の世界へ
足を踏み入れることに
足を踏み入れることに
対しては
不安よりも、
わくわく感の方が
強かったです。
アメリカ留学の思いが
アメリカ留学の思いが
どんどん膨らみます。
次回の留学体験記:
「なぜ、ニューヨーク?その3」
***
次回の留学体験記:
「なぜ、ニューヨーク?その3」